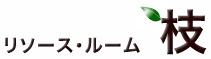枝レポート【余暇活動特集】
今回の枝レポートは【余暇活動】の中から、鑑賞後の感想の一部を集めてみました。
参加できなかった方も、せめて読んでイメージを広げ、興味を広げていただければと思います。
見出しは、伊藤が後から付けたものです。鑑賞の当日は、のんびり余暇を楽しんでいました。
花柳輔蔵さんのライブ『すたいるず+(プラス)』
『違った個性』を活かしあえたときの 心地よさ
花柳輔蔵さんがヒップホップダンサーや様々なジャンルのアーティストとコラボした
『すたいるず+(プラス)』のライブを観ました。
軽快な飽きさせない構成と、オシャレな感性があちこちに散りばめられた演出で、
感心したりドッキリしたり涙が出るほど笑ったり。
会場入り口の花々には三輪明宏、磯野貴理、小堺一機、松居直美、未唯(元ピンクレディ)をはじめ、
見たことのある名前がズラリ。・・・なるほど・・・。
有名な名取のお祖母様を持ち、しっかりした日本舞踊の美しさを基盤にした輔蔵さんの底力と柔軟な感性、
その魅力に惹かれて集まったアーティストの個性が繋ぎ合わされ、
響きあって、久しぶりに観応えのあるライブでした。
(M.M.記)
落語:『らく朝@健康落語』〈第二回〉
日本で『ただ一人』・・・ 意外な二足のわらじ
世田谷成城ホール会場は、満員の盛況。
「健康落語って何?」とよく質問されるそうですが、
簡単にいうとお医者さまが、落語をされるんですよ。
それも、現役の内科のお医者様!?が、落語家なんです。
日本広しと言えども医者と落語家の二足の草鞋を履いてる人は、らく朝さんただひとりでしょうね。
まず、最初は、スタンプトーク。初代林家三平さんが立って落語をして、
人気を博しましたが、立ったまま、おもしろくそして真面目に医学解説。
「あ」から始まって今回は「い」。
いと言えば「胃」にまつわる話かと思いきや、そんなに平凡ではないところが、
落語家の噺(はなし)。最後の健康落語は、ネタおろし「老いらくの恋」でした。
えっ「ネタおろしって何??」と思われたら、次回聞きに来て下さいね。
(M.I.記)
演劇『風が吹くとき』とアフタートーク&ミニライブ
『やめよう』が 言えることの大切さ
「核戦争が勃発するかもしれない」と言われてもピンと来ない人々
・・・でも、核のボタンが押されたら・・・。
日常が突然、非日常になり、放射能による汚染で心身が蝕まれ、死を迎える・・・
原作は静かな中にユーモアさえもあるイギリスの絵本で、アニメ化もされた作品の舞台化です。
難しい思想を語るのではなく、ただ、私たち人間は核のボタンを押すような愚かなことをしてはいけないと、
静かに訴えてきます。その愚かな行為の可能性がある時代だからこそ、
怖さを知り、一人一人の私たちが『やめよう』のひとことを言うことで、悲劇を止めて、
希望に満ちた未来に向かって生きていけるはず、というメッセージが力強く暖かく伝わってきました。
(J.H.記)
天野善孝さんの原画展
『ワク』が 意味を持つとき
ファイナルファンタジーのキャラクターデザインでも有名な天野さんですが、
ひとつ前の世代の方にはガッチャマン・ヤッターマンのキャラクターデザインがお馴染みかも知れません。
原画展といっても原画だけでなく版画(印刷されたもの?)が多数展示され、
30万、90万で何枚も売れていたのには驚きました。
会場説明員(というか、販売員・・・?)が
「版画だからこその美しさ、良さがあるでしょう?原画は、どうしても毛羽立ちなどが見えますし。」
と説明してきました。
絵本などの原画展では、
『本であるがゆえのイメージの広がりの限界(ワクのようなもの)をスルリと通り抜けて、広がっていく』
という感覚になり、その感覚が好きでした。
ところが今回は、説明員の言葉を「なるほど」と聞きながら、シャープに美しく仕上がった版画を見て、
もしかしたら、鋭い武器を持って戦うようなアニメやゲームの世界は、
ワクがあったほうが『安全』かもしれないと思ったのでした。
・・・・・・私は、毛羽立った原画のほうが温かみ(作者の体温)が感じられて、好きでした。
(T.I.記)
【余暇活動・・・に思う 人の不快感への気付きと 自分の不快感を乗り切るワザ 】
何を、どのように感じるかは、人それぞれです。好み(好き嫌い)もそれぞれ違います。
隣にいても同じ日本人でも、人が違えばその背景にあるものは微妙に違うのだから、
感じ方や好みは違って当たり前なのです。味覚・嗅覚・触覚(触感や食感)ということで言えば、
納豆が大好きな人もいれば、大嫌いな人もいます・・・これは文化的な背景も影響しているかも知れず、
そうなると文化の違いとも言えるかもしれません。
特に感覚に敏感な部分や鈍麻した部分がある場合には、思いがけないほど感じ方が違ってきます。
そして、その感じ方の違い(特に不快感)を理解して受け入れるのは、案外難しいことです。
自分は「そうでない」(嫌でない)状態で、平気で暮らしているのですから。
近頃は、自分から進んで新しい文化にふれることを苦手とする人が増えているかも知れません。
苦手なことをするときには、エネルギーをひどく消耗したりもします。
そして疲れ、避けるようになり、更に苦手になってしまうのです。
(・・・そのことに自分では気付けない場合もあり、知らないうちに辛さを積み重ねて、
ただただ苦しくなってしまう、ということもあります。)
そんな若者世代だからこそ、『気楽な仲間たち』と、いろいろな形で違った文化に触れる機会を増やして、
一緒に見たり聞いたり触れたり体を動かしたりしながら、何かを感じる
(『同じに』感じるのではなくてよいのだから)という体験をたくさんして欲しい・・・
面白いこと、楽しいことを増やすと共に、つまらないもの、嫌なものがあっても、
平静にやり過ごすワザ(スキル)を身につけて欲しい、と思っています。
他人との生活の中で、少しでも楽に生きていくために。
月別 アーカイブ
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2017年10月 (3)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年8月 (2)
- 2015年6月 (3)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (2)
- 2015年1月 (2)
- 2014年9月 (2)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (2)
- 2014年1月 (1)
- 2013年9月 (3)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (1)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (2)
- 2012年11月 (1)
- 2012年8月 (1)
- 2012年7月 (2)
- 2012年6月 (4)
- 2012年4月 (3)
- 2012年2月 (4)
- 2011年12月 (1)
- 2011年11月 (2)
- 2011年10月 (3)
- 2011年8月 (1)