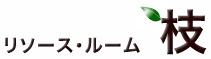事例から学ぶ Ⅴ 『親と子で どう生きていくか』~本人の自分理解と《親亡きあと》への道~
概要について
こちらのデータからご確認ください(pdfファイルが開きます)
講師紹介
白井 和子(しらい かずこ)
早稲田大学第一文学部文学科演劇専修在学中から映画製作に携わり、卒業後はプリンス自動車販売株式会社(現日産プリンス)に入社。日本自閉症協会の前身である自閉症親の会の発足当初より庶務・広報としての活動を続け、日本自閉症協会の機関誌「いとしご」や、自閉症ガイドブックシリーズの編集・制作に尽力する。平成20年12月発行の「自閉症の人たちのための防災ハンドブック」企画委員会委員長。「けやきの郷」評議員。
萩原 京子(はぎわら きょうこ)
幼稚園教諭として勤務ののち、十日市場で加藤醇子医師の診断を受けた自閉症の子どもたちへの指導を担当。その後、引き続き(社)神奈川学習障害教育研究協会の相談・指導室で発達障害がある人への継続支援を行う。2011年4月に指導室Momoを開設し、代表となる。発達障害・自閉症の地域訓練会スーパーバイザー。神奈川県の幼稚園・小学校を中心に、子どもたちの実態把握・事例検討なども行っている。
伊藤 逞子 (いとう としこ)
公立小学校通常学級の担任を経て、(社)神奈川学習障害教育研究協会に所属。国立特殊教育総合研究所のLDに関するプロジェクトや、文部科学省のLD・AD/HD・高機能自閉症の児童生徒に関するガイドライン策定に参加。2009年『リソース・ルーム枝』を開設。厚木市・大和市・町田市・武蔵野市等で専門家チームや巡回相談チームの一員としても活動。教育センターや特別支援学校等における事例検討・研修会講師の要請にも応えている。
講演会担当 井上 睦美 (いのうえ むつみ) (ひまわり教育研究所)